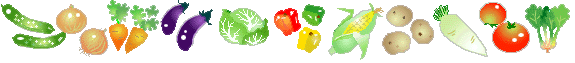きゅうり |
・うどんこ病・べと病に注意しましょう ・曲がり果や尻太果防止には、若どりをし、肥料を施して草勢を回復させます。 |
|---|---|
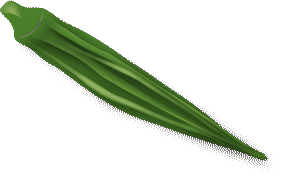 おくら |
・梅雨明けの頃、敷きわらや敷き草をし て、乾燥防止をはかりましょう。 ・下葉が込みあってきたら、着果節以下 1枚を残して摘葉します。 |
なす |
・乾燥を嫌います。敷きわらや敷き草をして乾 燥防止をはかり、ダニ類の発生を抑制しましょう。 ・秋なすを収穫するには8月上旬に更新剪定(切戻し)を行い、同時に肥料を施します。 |
トマト |
・多雨多湿を嫌います ・梅雨時期の疫病に注意しましょう ・尻腐れは、カルシウム(石灰)欠乏による生理障害です。 |